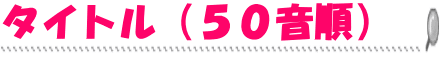
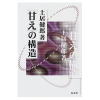 |
甘えの構造 日本人に特徴的な「甘え」を取り出し、主体的に一回だけの人生を生きるための指針を提示日本人論の古典としてロングセラー。ちょっと古いが、中世世代と付き合うには読んでおくと便利。 |
| 著者:土居健郎 | |
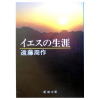 |
イエスの生涯 英雄的でもなく、美しくもなく、十字架に死んでいったイエスを遠藤が描き、感動を伝える。 |
| 著者:遠藤周作 | |
 |
生きのびるためのラカン よく噛んで読みましょう! |
| 著者:斉藤環 | |
 |
意識の形而上学 |
| 著者:井筒俊彦 | |
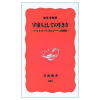 |
宇宙人としての生き方 宇宙的時間スケールで、人間の問題を読み解く |
| 著者:松井孝典 | |
 |
海の都の物語 塩野七生の作品の中で一番じゃないかと |
| 著者:塩野七生 | |
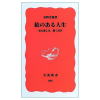 |
絵のある人生 例えば、素人(あるいはサル!)が描いた、訳の分からない抽象画は芸術と言えるのか・・・。絵についていろいろ考えさせられる本です。 |
| 著者:安野光雅 | |
 |
沖縄ノート 先の世界大戦で「沖縄」はいかなる状況下にあったのか。大江がルポルタージュ風に描いた一冊。最近、この書物を巡って行われた裁判が話題となったが、真実を知るためにも一読の価値あり。 |
| 著者:大江健三郎 | |
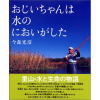 |
おじいちゃんは水のにおいがした こんなスローな生き方をしている人々が、実際にお隣の県におられるという事を知ってもらうのに最高の本ではないかと、滋賀県民の私は思う次第です。 |
| 著者:今森光彦 | |
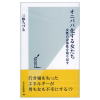 |
オニババ化する女たち 将来の自分たちのことだよ! |
| 著者:三砂ちづる |
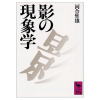 |
影の現象学 |
| 著者:河合隼雄 | |
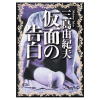 |
仮面の告白 是非一読をお勧めします。 |
| 著者:三島由紀夫 | |
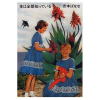 |
体は全部知っている |
| 著者:よしもとばなな | |
 |
カラマーゾフの兄弟 上・中・下 「積ん読本」の典型なので、全巻読破したら皆に偉いと褒められる。不眠症にも良薬。 |
| 著者:ドストエフスキー | |
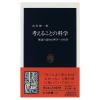 |
考えることの科学 たとえば、直感が正しいこともあれば、よーく考えたのに間違うこともあります。何故なんでしょう・・・。このようなことを考える本です。 |
| 著者:市川伸一 | |
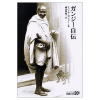 |
ガンジー−自伝 大学生として、やはりガンジーの事を知らないわけにはいかないのではないか、と思います。 |
| 著者:ガンジー | |
 |
菊と刀 文化人類学の古典にして、日本人論の古典でもあるロングセラー。酷い誤解も多々あるが、一度も日本に行かないでこれだけ分析するとは、アメリカ人恐るべし。 |
| 著者:ルース・ベネディクト | |
 |
犠牲 生きること、死ぬことと真摯に向かい合えます。 |
| 著者:柳田邦男 | |
| 旧約聖書 |
|
 |
「教養」とは何か |
| 著者:阿部謹也 | |
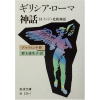 |
ギリシア・ローマ神話 キリスト教の知識と並び西欧では基層文化なので、外人と話すには教養として必要。 |
| 著者:ブルフィンチ | |
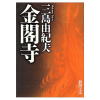 |
金閣寺 |
| 著者:三島由紀夫 | |
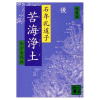 |
苦海浄土 |
| 著者:石牟礼道子 | |
 |
グレート・ギャッツビー 大学の時に読まされたのですが、今や米文学の古典ですよね。同じく Lost Generation のヘミングウェイが入っているので不要と思われるかも知れませんが、個人的には、こちらの方を推したいです。 |
| 著者:S.フィッツジェラルド | |
| 源氏物語 |
|
| 著者:紫式部 | |
| 古事記 上・下 |
|
 |
ことばが劈かれるとき |
| 著者:竹内敏晴 |
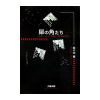 |
犀の角たち 短大図書館にしか所蔵がないので推薦しにくいのですが、「仏教と科学のつながり」を扱ったこの本は、ここ数年読んだ本のなかでもっとも刺激的で面白くてわかりやすい文章が展開される名著だと思っているので強く推薦します。 |
| 著者佐々木閑 | |
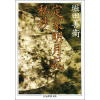 |
定家明月記私抄(正・続) 同じ著者の「路上の人」と合わせて読むと面白い。 |
| 著者:堀田善衛 | |
| 文明の旅 サハラ幻想行 文化・心理の両面から考察する面白さがある。 |
|
| 著者:森本哲郎 | |
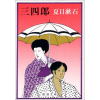 |
三四郎 大学生活にぴったり。 |
| 著者:夏目漱石 | |
 |
失敗の本質〜日本軍の組織論的研究〜 |
| 著者:戸部良一 | |
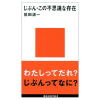 |
じぶん・この不思議な存在 |
| 著者:鷲田清一 | |
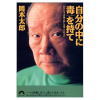 |
自分の中に毒を持て |
| 著者:岡本太郎 | |
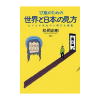 |
17才のための世界と日本の見方 世界の文化や思想と日本のつながりが分かる。 |
| 著者:松岡正剛 | |
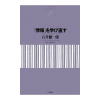 |
「情報」を学び直す 今こそ「情報」のキホンを学ぶ直すべきだと思います。情報の本質とは?コミュニケーションとは? |
| 著者:石井健一郎 | |
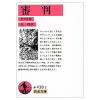 |
審判 是非一読をお勧めします。 |
| 著者:カフカ | |
| 新約聖書 キリスト教の聖典。イエスや使徒の行動やメッセージが記され、人生や世界観を知る上で深い示唆がある。 |
|
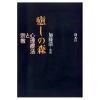 |
心理療法と宗教 宗教と心理療法との肉体的因果は・・・ |
| 著者:加藤清 監修 | |
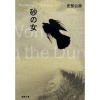 |
砂の女 |
| 著者:安部公房 | |
 |
青春の門(第一部)筑豊編 高校生の時、この本を読むのが流行りました。若干、血沸き肉踊る場面もありますので、読書嫌いの学生さんも必ずや読んでくれるのではないか、との淡い期待を抱いて推薦します。 |
| 著者:五木寛之 | |
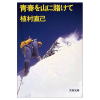 |
青春を山に賭けて 人見知りの「どんぐり」と呼ばれた冴えない男が、泥臭い不断の努力を続けた結果、世界最高のアルピニスト/冒険家の1人に成長するというのが何と言っても勇気を与えますね。野口健さんも大きな影響を受けた本ですよね。 |
| 著者:植村直己 | |
 |
精神分析入門 上・下 心理学に関係なくても教養として基本。『夢判断』でもいいが、フロイトくらい読んでいないと現代人失格。臨床心理学を学ぶにはまずこの本を読まずして、臨床心理学の学生とはいえないほど重要な本。Kの本を読むと他の人の考えも分かりやすくなる。 |
| 著者:フロイト | |
 |
生物と無生物のあいだ 生命とは、生きているとはどういうことか、考えるきっかけになるのでは? |
| 著者:福岡伸一 | |
 |
世界史とわたし〜文明を旅する〜 |
| 著者:梅棹忠夫 | |
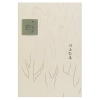 |
センセイの鞄 素晴らしい本です。 |
| 著者:川上弘美 | |
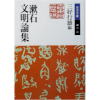 |
漱石文明論集 |
| 著者:夏目漱石 | |
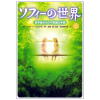 |
ソフィーの世界 哲学者からの不思議な手紙 上・下 |
| 著者:ヨースタイン・ゴルデル | |
 |
空と風と星と詩 個人的に、韓国/朝鮮人による著作を一冊入れねばならないと思ったのですが、不勉強でこの人位しか思い浮かびません。京都にゆかりのある人物であり、その生涯は必然的に日韓の現代史にリンクします。 |
| 著者:尹東柱詩集 | |
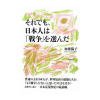 |
それでも日本人は「戦争」を選んだ 日清戦争から第2次世界大戦まで、日本が行った戦争と日本人の関わりを解説する。 |
| 著者:加藤陽子 | |
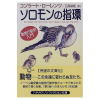 |
ソロモンの指環 動物行動学言われて興味はなくとも、面白いからスラスラ読める。動物の気持ちが分かるようになる。海外でも人気。外人はみんな読んでるよ。 |
| 著者:コンラート・ローレンツ |
 |
代表的日本人 |
| 著者:内村鑑三 | |
 |
種の起源 |
| 著者:ダーウィン 八杉龍一訳 | |
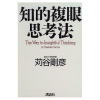 |
知的複眼思考法 |
| 著者:苅谷剛彦 | |
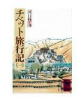 |
チベット旅行記 1〜5 外人の入国は死刑という時代に、現地語を完全習得、現地人に化け厳寒の山河を越えての単独行。なんという一念。人類学者も深々と一礼の偉大な記録。 |
| 著者:河口彗海 | |
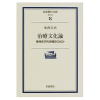 |
治療文化論−精神医学的再構築の試み− |
| 著者:中井久夫 | |
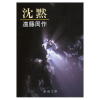 |
沈黙 神の沈黙という永遠のテーマを投げかける重い作品です。でも、一読の価値あり。キリスト教のことが分かります。 |
| 著者:遠藤周作 | |
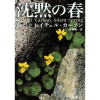 |
沈黙の春 環境本の古典かつ教養書でもある。今から思えば警告の的中度の高さは凄いもんだ。 |
| 著者:レイチェル・カーソン | |
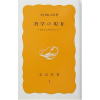 |
哲学の現在 |
| 著者:中村雄二郎 | |
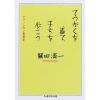 |
てつがくを着て、まちを歩こう ファッションやオシャレは好きだけど、哲学なんて興味ない・・・という人は是非一度読んでみてください。 |
| 著者:鷲田清一 | |
 |
デモクラシーの冒険 民主主義とは?世界の流れをどう従えば良いか?対談形式で読みやすい。語句説明も充実。 |
| 著者:姜尚中 |
 |
なぜ勉強するのか? |
| 著者:鈴木光司 | |
| 日本書紀 上・中・下 |
|
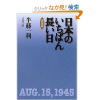 |
日本のいちばん長い日 太平洋戦争の最終日−昭和20年8月15日の一日を描いたノンフィクション |
| 著者:半藤一利 | |
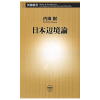 |
日本辺境論 |
| 著者:内田樹 | |
 |
ねじまき鳥クロニクル 1〜3 村上ワールド独自の軽い筆遣いの中に、ショッキングな形で過去の日本と中国との関係が描きこまれています。長いけれども、彼の戦争の捉え方が分かる作品です。 |
| 著者:村上春樹 | |
 |
寝ながら学べる構造主義 |
| 著者:内田樹 |
 |
排除の構造 希望が持ちにくい、閉鎖的な社会状況の中で自らを相対化するために読んでほしい。 |
| 著者:今村仁司 | |
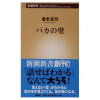 |
バカの壁 「俺のことじゃん!」と思う人、思える人は読まなくても大丈夫。「ああ、あいつのことだ・・・」と思って読みましょう。精神衛生のために・・・ |
| 著者:養老孟司 | |
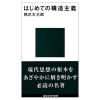 |
はじめての構造主義 現代思想の見取り図を明解に解説。優れた教養書。 |
| 著者:橋爪大三郎 | |
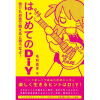 |
はじめてのDIY:何でもお金で買えると思うなよ! 図書館に所蔵されていないのですが、過剰な消費主義社会に生きる今の学生さんたちに強く薦めたい本のひとつです。自分たちの創意工夫で現代社会を生き抜くための知恵というものをセンス良く提示している本です。 |
| 著者:毛利嘉孝 | |
 |
働き方革命 |
| 著者:駒崎弘樹 | |
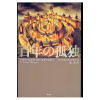 |
百年の孤独 これは、単純にラテンアメリカの作家がいないように思っていたので有名な書籍を入れたのみです。 |
| 著者:ガブリエル・ガルシア=マルケス | |
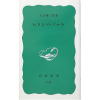 |
ヒロシマ・ノート 『沖縄ノート』と対をなす一冊。大江の個性的な文体が、時に我々の理解を阻むが、日本が蒙ったもう1つの不幸について若き作家がいかなる思いを抱いたか知ることができる。 |
| 著者:大江健三郎 | |
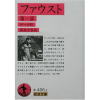 |
ファウスト(第一部・第二部) |
| 著者:ゲーテ | |
 |
風土 |
| 著者:和辻哲郎 | |
 |
福翁自伝 |
| 著者:福沢諭吉 | |
| 不思議の国のアリス 児童書のイメージが強いが、本当は奥が深いキャロル。大人になって読むとまたひと味違う。 |
|
| 著者:ルイス・キャロル | |
 |
武士道 |
| 著者:新渡部稲造 | |
 |
ブッダのことば |
| 著者:(訳)中村元 | |
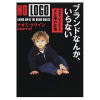 |
ブランドなんか、いらない この本も、近年における消費主義やグローバル資本主義社会をいかに生き抜くかという観点で重要な著作です。できるだけ若いうちに触れておいたほうがいいテーマかと思うので学生さんにお勧めしたいです。 |
| 著者:ナオミ・クライン | |
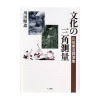 |
文化の三角測量 文化から社会を捉えなおすために必要な本 |
| 著者:川田順造 | |
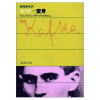 |
変身 カフカの代表作であり、若い人には共感しやすい。もの凄く薄いので簡単に「ま、カフカは読んだな」と人に言える、コストパフォーマンスの極めて高い本。 |
| 著者:カフカ | |
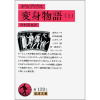 |
変身物語 上・下 なぜ変身しようと思ったのか・・・神話だの仏典だの昔話は、よく読むと思い切り笑えるのだ。その背後にエートスがキラリ。お楽しみください。 |
| 著者:オヴィディウス |
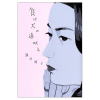 |
負け犬の遠吠え 将来の自分たちのことだよ! |
| 著者:酒井順子 | |
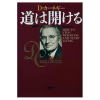 |
道は開ける A.カーネギーの『自伝』よりかは、似た名前のD.カーネギーのこの本を薦めた方が、若い学生さんにはより有益かと思います。「心理療法」や「カウンセリング」だけが人の悩みを解決するのではない、という観点も重要です。 |
| 著者:D・カーネギー 香山晶訳 | |
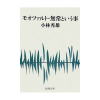 |
無常ということ 教養として必読書です。 |
| 著者:小林秀雄 | |
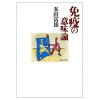 |
免疫の意味論 |
| 著者:多田富雄 | |
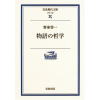 |
物語の哲学 歴史哲学にとどまらず、社会を捉えなおすために必要な本。 |
| 著者:野家啓一 | |
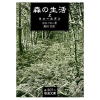 |
森の生活 スローでエコな生活を考えるにあたって、素晴らしいヒントが記されている古典だと書店に記されていました。 |
| 著者:D.H.ソロー |
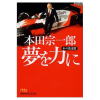 |
夢を力に−私の履歴書− この方の晩年のインタビューが日本語教材になっており、それを前の職場の日本語学校で使用していたことを思い出したのですが、「日本的精神性」のプロジェクトにも、単に古典とか伝統芸能だけではなく、こうしたものづくりの職人の系譜も取り上げてほしいものだと思います。 |
| 著者:本田宗一郎 | |
 |
ユング自伝 上・下 ユング心理学入門と合わせて読んでください。 |
| 著者:A・ヤッフェ(編) | |
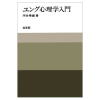 |
ユング心理学入門 |
| 著者:河合隼雄 | |
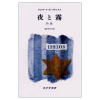 |
夜と霧 一昔前は大学生の必読書だったが、現在でもホロコースト本の一冊は押さえておくべきだろう。その意味で好適。人生を切り開く案内書としても読める。泣くけど。 |
| 著者:ヴィクトール.E.フランクル |
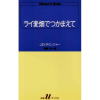 |
ライ麦畑でつかまえて 高校生の必読書。歳をとると感性が合わなくなるので、未読の人は読んでおいたほうがいい。欧米でも基本書。 |
| 著者:J.D.サリンジャー | |
 |
竜馬がゆく 1〜8 |
| 著者:司馬遼太郎 | |
 |
リンゴが教えてくれたこと この人はマジですごい人だと、NHKの番組を見て思っていたのですが、書籍に関してもこれが読ませるのです。淡々とした語り口の文章も巧みです。リンゴが実るまでの壮絶な人生を知るだけでも感動します。 |
| 著者:木村秋則 | |
 |
老人と海 ヘミングウェイを好きでない私も文句なしに絶賛。短編としての完成度の高さは白眉。巨大な魚と戦う老漁師の生きざまが、目的に向かってチャレンジする人間の在り方として感動させられる。 |
| 著者:ヘミングウェイ | |
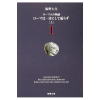 |
ローマ人の物語 1〜15 ヨーロッパの原型となるローマの歴史がおもしろく語られて、ローマ人の考え方が良くわかる。 |
| 著者:塩野七生 |
 |
「わからない」という方法 わからない、ということは、決して恥じることではありません。大学は教員も学生も、ともに分からないところをお互いで考え合う場所です。そのような意欲的な挑戦が皆さんの学生生活を豊かにしてくれるはずです。 |
| 著者:橋本治 |