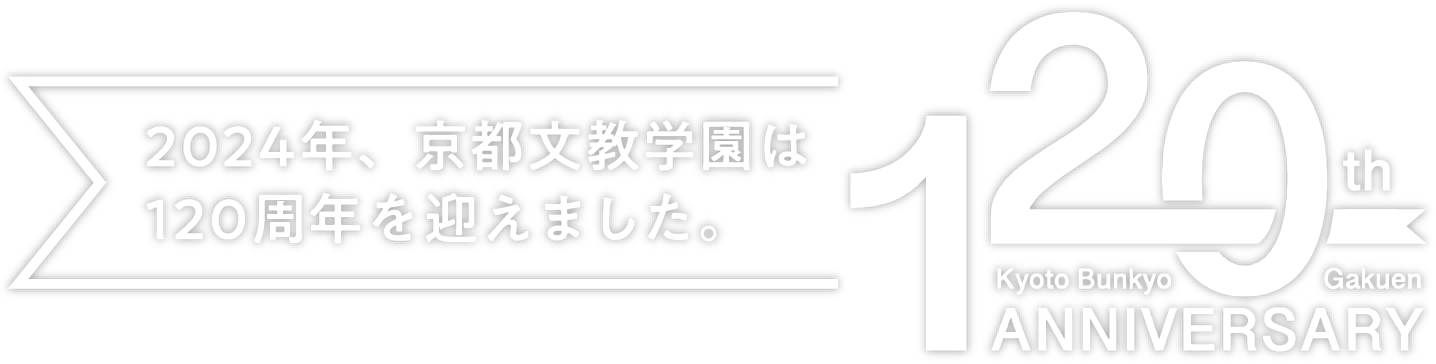
京都文教120周年特別企画
卒業生を訪ねるプロジェクト
起業家・原田尚美さんに聞いてみました
いまのお仕事と京都文教で学んだこと

京都文教大学卒業生(2006年3月 文化人類学科卒業)
起業家・山口市地域おこし協力隊
やまぐちシードル代表
原田 尚美さん
山口市出身。「自分にしかやれない仕事をしたい」、「地元山口市の魅力を体感できる場所をつくりたい!」と一念発起し、地域おこし協力隊として地元に戻る。ワインが好きで、醸造家のお話しを聞き、ワインが育った環境や空気感にワクワク!
こんなワクワクする場所をつくりたいと考え、地元のりんごを使用したスパークリングワイン「山口シードル」の製造・販売事業に取り組んでいる。令和4年度総務省「ふるさとづくり大賞」 個人表彰(総務大臣表彰)を受賞。
山口シードル
https://yamaguchi-cidre.net/
インタビュアー

京都文教大学 総合社会学科 メディア・社会心理コース4年
メディアと社会心理を中心に学びながら心理学も学んでいます。卒論研究では投票率について研究しています。

京都文教大学 総合社会学科 メディア・社会心理コース4年
メディアがどのような影響を与えているのか、日常生活における人々の行動や思考について学んでいます。他にも別のコースが受講可能なため、経済学や観光についても学んでいます。
外の世界に目を向けた学生時代。
素敵な出会いに恵まれました。

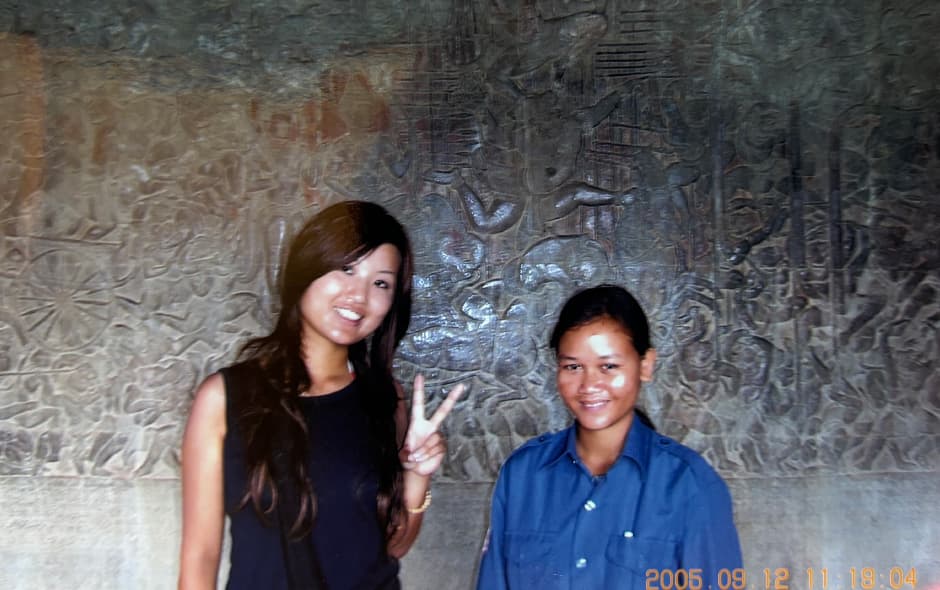
河村さんどうして地元の山口市を離れて、京都文教大学に進学しようと思われたのですか?
原田さん正直、外の世界を見てみたいというのがありきで、京都にこだわっていたわけではありませんでした。京都文教大学のことを知った時に、異文化を体験できる環境が魅力的に見えて、せっかく外に飛び出すなら世界まで視野を広げたいと思って京都文教大学に入学しました。
深尾さん当時からアクティブな性格だったんですね。
原田さんいえいえ、全然! もともとは内気な女の子だったんですよ(笑)。そんな私が京都文教大学に行って、フィールドワークや国内外の旅行などでいろんな場所に行って、たくさんの人と出会って、それが素敵なことだと学んだから変われたんだと思います。

河村さん学生時代はどんなことが思い出に残っていますか?
原田さんやっぱり一人暮らしは新鮮で楽しかったですね。友人とごはんを作ったり、誰かの家でおしゃべりをしたり、ただ一緒にいるだけで満たされるような楽しい時間でした。また、外に出ることに抵抗を感じなくなっていたので、長期休暇には友達と海外旅行でカンボジアを訪問したり、バックパッカーとして沖縄を回ったり、新しい世界を見て回るのが好きでしたね。そこにはいつも新しい出会いや発見があります。例えば、沖縄では美しい海を守る運動をしている人たちと出会って、それがきっかけで観光と自然保護の関係を調べるようになりました。結局その研究が私の卒業論文になったので、どこに転機があるのかわからないものですね。
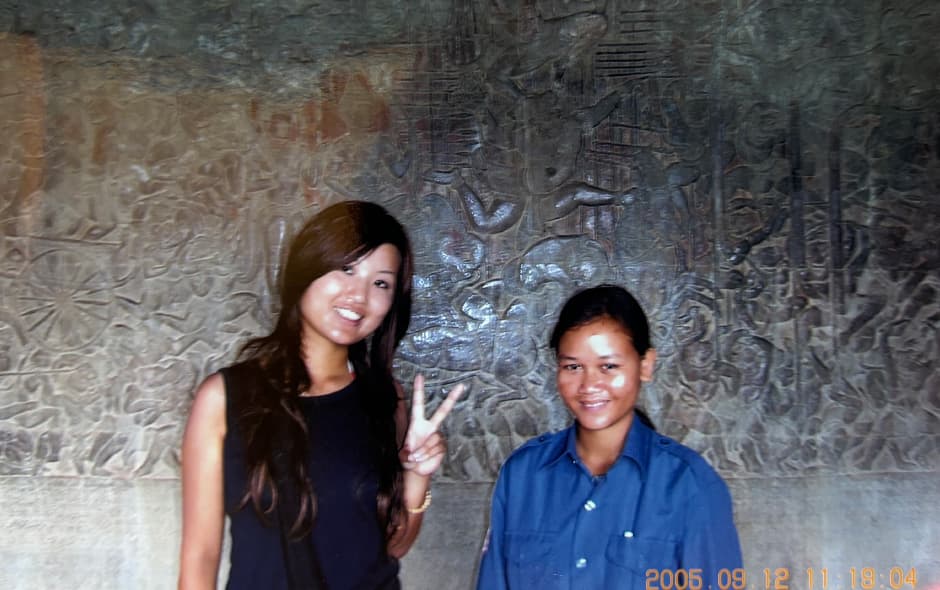
深尾さん原田さんから見て、京都文教大学に魅力はどんなところだと思いますか?
原田さんそれは間違いなく人と人との距離が近いことですね。小さな大学だから学生同士がみんな顔見知りだし、先生や職員のみなさんも親身になって学生の面倒を見てくれます。現在は学長を務める森正美先生のゼミに所属していたのですが、勉強以外にもいろいろなことに相談に乗ってもらっていました。学生時代ってプライベートや進路のことなど、いろいろと悩みが尽きないじゃないですか。それをゼミの先生に、何の気兼ねもなく相談できたのって実はすごいことだと思うんです。冗談みたいなやりとりも多かったけど、例えば、私が就職活動で弱音を吐いたら、就職することの意義を説いて励ましてくれました。学生と同じ目線に立ちながらも、進むべき道を示してくれる大人がいつも傍にいてくれたことは、私にとってとても幸せなことだったと感じています。今回のこのインタビューも、学生時代にお世話になった当時の就職進路課の職員の方からお話をいただいて、本当はあまりメディアに出るのは得意ではありませんけど、あの時に寄り添っていただいた職員の方に恩返しができるのなら…と受けさせていただきました。
運命に身を委ねて帰郷して、
名産となるシードル造りに挑戦!
河村さん山口市に戻って起業されるまでの流れを教えていただけますか?
原田さん卒業してからは関西に残って一般企業に就職しました。仕事は楽しかったし、それなりに充実した日々だったけど、自分ではなくてもできる仕事に思えてしまって、心のどこかで虚しさも感じていました。そんな時に「山口市地域おこし協力隊」の募集を知って、「これは運命かもしれない!」と思い切って帰郷することにしました。
深尾さんずいぶんと思い切った決断ですね!

原田さん会社員時代はパソコンとにらめっこが多かったのですが、京都文教大学で学んだ「なんでもやってみる精神」は大切にしていたので、週末のプライベートでは里山保全活動やぶどう園の援農ボランティアなどに参加するなど、気になることには積極的に挑戦していました。ワイナリーなどと関係を持つうちに「農業」「食」「健康」などのキーワードに興味を持つようになったので、地域おこし協力隊は絶好の機会だと思ったんです。また、他の地域ならともかく、私の地元の山口市は「私がやらなくちゃ誰がやる」という想いが強かったので、使命感を持って挑戦してみることにしました。

河村さん地域おこし協力隊について教えていただけますか?

原田さん地域おこし協力隊のミッションは、3年の任期で「山口市の地域特性を踏まえたビジネスモデル構築」というものでした。会社員時代の援農ボランティアで、コミュニケーションツールとしてのワインに大きな可能性を感じていたので、ワイナリーを作りたいと考えていたのですが、ワイン造りは手伝った程度だし、ぶどうも育てられない、経営の経験もないという状態だったので手探りからのスタートでした。起業塾に通って起業までのプロセスや収益構造などについて学びながら、どうにか起業までたどり着いたという感じです。ただ起業塾では私と同じように熱い想いを持った仲間と出会うことができたので、そういう人たちと励まし合いながら学べたことは大きな収穫だったと思います。

深尾さんワインを造る予定がどうしてシードルになったのですか?

原田さんまずは山口市内でぶどうを植える土地を探していたところ、りんご農家さんとの出会いがあってそれが大きな転機になりました。シードルとはりんごでできたスパークリングワインのことです。りんごを使った商品を開発したいという農家さんの思惑と、お酒を作りたいという私の想いが一致して、シードル造りに挑戦することになりました。また、ワインなら他にも競合がたくさんいますが、シードルはまだそれほど知られていませんし、山口市の阿東徳佐地域は西日本最大級のりんごの産地です。そこで栽培されている「徳佐りんご」を使ったシードルなら、山口市の新しい名産品になる可能性を秘めているのではないかという期待があったので、挑戦することになりました。

河村さん山口市の魅力を再発見できるような素敵な取り組みですね。

原田さんまさにその通りで、起業するにあたっては、山口市にどんな魅力があるんだろうと見つめ直すことから始めました。山口市には何もないように思われがちですけど、実は海の幸、山の幸に恵まれていて、スーパーに売られている魚や野菜でさえも新鮮でとってもおいしいんです。その魅力を引き立てるお酒があれば、さらに料理を楽しめるようになって独自の食文化に発展するのではないかという着眼点を大切にしています。ワインの世界では「マリアージュ」や「ペアリング」と言われる考え方で、それを山口市の食文化に当てはめながら料理を引き立てるようなお酒造りに挑戦しています。

深尾さんシードルとしてはどんな特徴があるのですか?
原田さん料理とのマリアージュを大切にしているので、基本的に引き立て役として低アルコールの飲みやすいシードルを作っています。海の幸、山の幸とのペアリングを意識した「UMI」「YAMA」というシードルに、新たに「KAZE」というシリーズが加わって、主に3種の「やまぐちシードル」として商品展開をしています。「KAZE」は2020年の台風がきっかけで生まれた商品で、風で青いまま落ちてしまったりんごは商品価値がないだけではなく、拾って穴を掘って埋めるというマイナスの作業が発生しています。それを安く買い取ってお酒の原料にすることで、農家さんにとっても、私にとっても、Win-Winの関係を構築することができています。農家さんから「助かっています」という言葉をいただいた時には、微力ながら地域に貢献できたのではないかとやりがいを感じることができました。
河村さんラベルもかわいいし、お土産にぴったりですね。
原田さんありがとうございます! 私にとっては何千本のうちの1本であっても、お客様にとってはその1本だけの大切な贈り物だという意識を大切にしています。ラベルのデザインにもこだわっていますし、自分でラベルを貼って梱包もしているのですが、1本1本を大切に、どうすればきれいに見えるのかを考えながら仕事をするようにしています。
挑戦することで未来は開ける。
失敗なんて恐れなくていい。
河村さん原田さんのこれからについて教えていただけますか。

原田さん最近では若い女性を中心に少しずつシードルの知名度も上がってきて、私が造っている「やまぐちシードル」も駅の特産品コーナーに置いていただけるようになりました。もともと「やまぐちシードル」が商品として完成したのが2020年のコロナ禍で、会合や会食が制限されていた時期だったので、「食とのマリアージュを広めたい」というコンセプトがなかなか伝えられる機会に恵まれませんでしたが、これから新たにショップを立ち上げるなどして、「やまぐちシードル」の世界観を伝えていきたいと考えています。飲食店とのコラボレーションなども企画して、シードルを通じて山口市の魅力を再発見できるような機会を提供していきたいですね。

深尾さんでは、最後に在学生にメッセージをお願いできますでしょうか。
原田さん新しいこと、自分が興味があることにどんどん積極的にチャレンジしてほしいと思います。新しいことに挑戦するのは誰だって怖いと思いますが、挑戦してみないことには自分に何が合うのかなんて見えてこないと思います。失敗したって全然かまわないし、そこに何かしらの気付きがあったならそれは失敗ですらないと思います。本当の失敗は挑戦しないこと。できるかどうかを思い煩って立ち止まってしまうことの方がずっと問題だし、もったいないと思います。私も大学を卒業してから会社員時代を経て現在に至るまで、紆余曲折を経てずいぶんと長い時間がかかりました。もちろん起業するまでにはお酒の勉強をしたり、資金繰りを考えたり、大変なことはたくさんありましたし、今もどうやってりんごを仕入れようとか日々いろいろな課題に直面しています。それでも自分の理想があって、それに向かって突き進むのみなのでちっとも苦ではありません。それよりも仕事をしながら、「自分って何なんだろう」と漠然と思い悩んでいた時期の方がよっぽど辛くて苦しかったように思います。やりたいことを見つけるのはきっと誰にとっても簡単なことではありませんが、私はシードルがあったから自分を見つめ直して、何がしたいのかを考えるきっかけをもらうことができました。私にとってのシードルのような出会いが、きっとみなさんにも訪れるはずですのでどうかがんばってください。




取材を終えて

今回お話を聞かせていただく中で「マリアージュ」という言葉をたくさん聞きました。マリアージュとはお酒と食事のフードペアリングのことです。そのくらいそこに重きを置き、山口のおいしい野菜や果物をシードルを通して知ってほしいという思いで今までやってこられたんだなということが伝わってきました。原田さんがかなえたい思いをもって地元で起業されこれまでやってこられたのを見て、私も自分のやりたいこと、叶えたいことにもう一度向き合ってみようと思うきっかけになりました。

原田さんの貴重なお話を聴き、何事にも挑戦することと沢山の人と出会い、交流する大切さを感じました。原田さんは大学時代に東南アジアへ何度か旅行をされており、勢いで海外旅行に行っていたとおっしゃられて、行動力の凄さを感じました。恐れずに挑戦されていて、私も見習いたいと思いました。また、大学の長期休みでは沖縄でバックパッカーをされており、色んな方と出会いがあり人それぞれの生き方というのを感じたとおっしゃられていて、人との出会いの素晴らしさを感じました。
